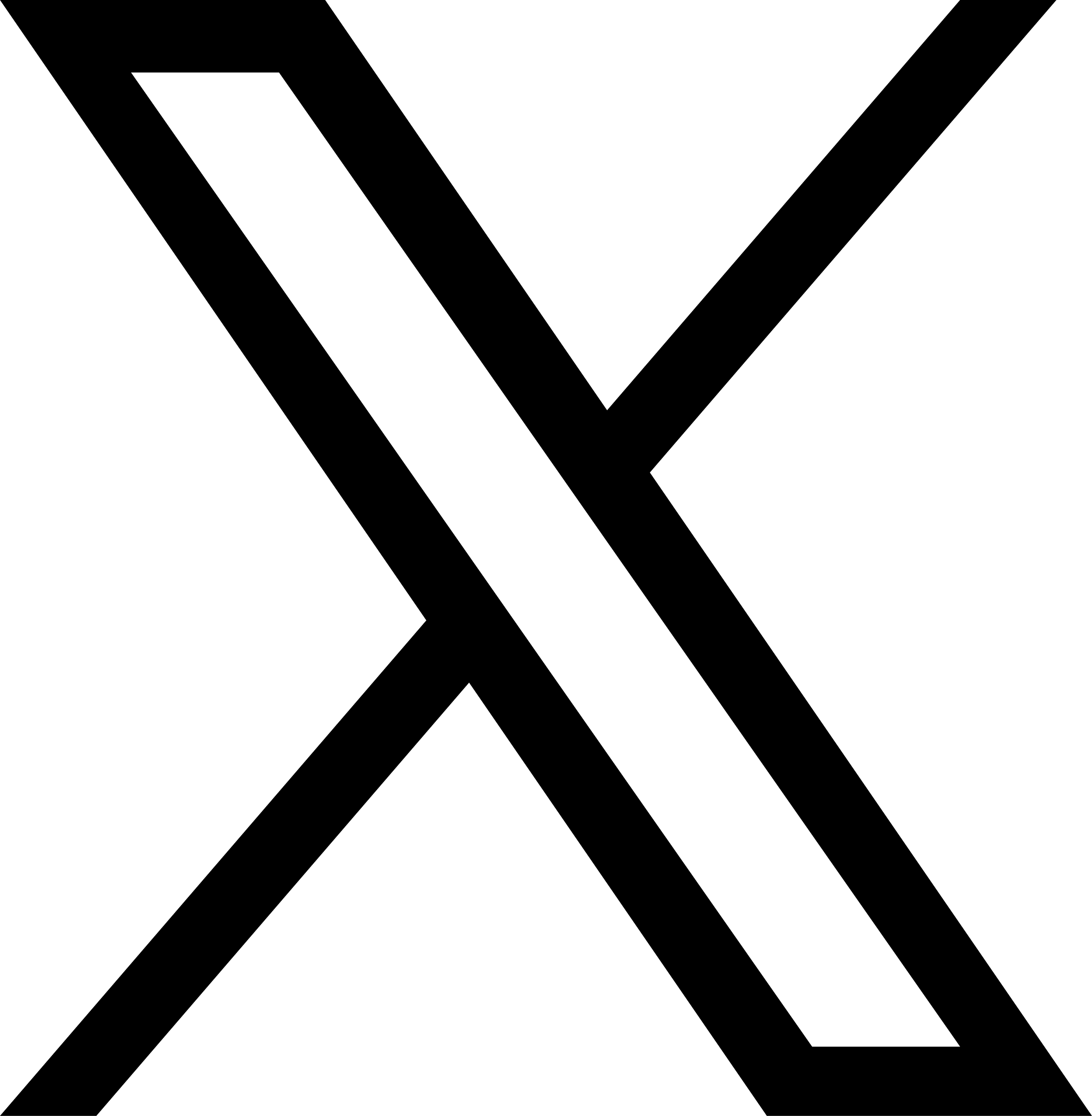「ちょこっと京都に住んでみた。」(ギャラクシー賞奨励賞、ATP上方番組大賞 グランプリ)、「名建築で昼食を」(日本民間放送連盟賞 優秀賞)、「À Table!」(ATP賞テレビグランプリ 奨励賞)、「京都のお引越し」(東京ドラマアウォード ローカル・ドラマ賞)、「マニアさんと歩く関西」、これらのタイトルを見てピンとくる方はいらっしゃるだろうか。それぞれ別の放送局で放送されたドラマではあるが、実はすべて同じチームによって制作されている。どの作品も、どこか静かな空気が流れ、見ると幸せな気分になる。
これらを作った中心人物は、プロデューサー・清水啓太郎さんと監督・吉見拓真さん。清水さんが中心となりドラマの企画を立てて、放送局に提案し、番組を作っている。特定のチームで、ここまで多くの作品を制作することはかなり珍しいそう。
いい意味で、共通する「良さ」がある。見たとたんに「これは同じチームの制作では?」と気が付く。いったいどうして、出演者やテーマが異なる中で毎回、こんなにも素敵な作品たちが生まれるのだろうか。
そんな思いを抱いていたみんなドラマ編集部が、このたび、BS松竹東急で、2024年7月クールに放送された連続ドラマ「À Table!~ノスタルジックな休日~」について、お二人へのインタビューを敢行。Amazon Prime Videoなどでの配信がスタートするタイミングで、「À Table!」の魅力を掘り下げるとともに、過去作品にもさかのぼり、その制作の秘密に迫りました。(第1回目/2回)
夫婦がご飯を作って食べる姿を通して「時間」や「繋がり」を感じるドラマに
――まずは「À Table!」のお話から。今回、初めて食、レシピが題材になっています。
清水「元々シーズン1のときに、原案の『歴メシ!決定版 歴史料理をおいしく食べる』が面白いなと思っていてね。学術的に正確に再現するのではなくて、夫婦が身近な素材でご飯を作るという話が良いなと。同時に、歴史の人物がとても身近に感じられる話だったので、これは美味しい料理を紹介するんじゃなくて、時間をテーマに、長い時間を経て、先人たちの知恵が今に繋がってるということを感じられる話を作ろうと思って」
.jpg)
――食そのものより、その先にある「時間」や「繋がり」がテーマ。
清水「そう。そこに『量子力学』などの最新の物理なんかの話を加えてみたり。僕は自分の知らない話を読むのが好きで。今は、自分が中学高校で学んだ頃から40年以上も経っているので、昔勉強したときとは全然違っていて、そういった今の知識を入れ込んでみたり。それと、いつも哲学の話を何となく散りばめるので、今回も老子とかプラトンとか、自分が心に残っている言葉を混ぜてみたり」
藤子不二雄さんのように!? 二人三脚で作るプロット、ストーリーと脚本
――具体的なプロットやストーリーはどのように?
清水「大体は主に初めのプロットやストーリーラインは僕が書くんだけど、物語の場所だったり、今話したようなトピックスを踏まえて、脚本の横幕(智裕)さんがそれを受け取って全体をまとめて初稿を書きます。でも、まずはキャラクターかな。半径3メートルの世界というか、登場人物は大体、身近な人から聞いた話だったり、周りにいる人だったり、3人から4人くらいの僕の知っている人から、この部分はこの人、そっちはあの人、みたい感じで一人のキャラクターを書いていき、そこに横幕さんが加筆して膨らませます。ジュン(市川実日子)もヨシヲ(中島歩)もそう。『名建築〜』の時のカフェのくだりも知り合いの話をアレンジしてるし。実際の話は仲良くお店開業したんだけどね」
吉見「ヨシヲは、清水さんの友達で、実際に漬物メーカーに勤めている方がいらっしゃいまして。ある日突然、登場人物のモデルにしようと思っている人とミーティングするから、と言われて話をしましたね。こういうことはわりとしょっちゅうあります」
清水「『ちょっと会って喋って』みたいな」
吉見「そういう意味ではスーパーリアルかもしれない。キャラクターの性格を考えて、それを造形してお話を作っていくのが清水さんと横幕さんのベースなので」
清水「ケースバイケースですけど、そうやって一番最初に自分で作る、この人はこんな人っていうキャラクター表というものがあります。で、例えば主人公の感情の流れ、初めに思っていた「楽しいっていう価値観」のところから、最後、感情が動いて価値観が変わるみたいな大きな流れは、考えた上で、横幕さんと一緒にロケハンしたり、話をしたり。そこから、ストーリーラインとかプロットラインを書いたりする。横幕さんから、この話にこのご飯とこの場所をくっつけた方が、一つの話になるよね、なんて膨らましてもらってアレンジが加わったりもします。そこはさすがと思うところです。それを台本にしてもらって、こっちで触ったり、一緒に直したりとかしながら。だから初稿は全部、横幕さんが書いている感じですね」
――二人三脚、ですね。
吉見「清水さんがいなかったらできないし、かといって横幕さんがいなかったら違う人がいるかというと、そうでもない」
清水「そうそう独特なんです。本当に藤子不二雄さんみたいな…ちょっと比べる人が巨匠すぎますけれども。今回みたいに、登場人物が出かける場所があると、そこを一緒に回って、こんなこと考えてるとか、多分こんな話とか、いろいろお互いに話をしながら。本当、一緒に作っている」
市川実日子さんと中島歩さんが台本と向き合って紡ぎ出す会話
――シーズン2の「~ノスタルジックな休日~」では、ジュンとヨシヲが毎回いろんな場所へ散歩に出かけますね。
清水「芋の子を洗うような場所はきっと苦手な夫婦だと思う。東京の、人のいないところを探して遊んでいるっていう設定かな」
吉見「そういう、いい場所とかいいお店とか、自分がエエなと思うところで、なおかつ“世間からまだ見つかっていない場所”って、エエじゃないですか。好きやなと思う。僕もそうだし、清水さんもそうだし。それを隠しとけばいいのに、やっぱり言いたいんですよね(笑)」
清水「いや、ネタに困るから身を切っているだけ(笑)」
.jpg)
吉見「でも、知られたところで楽しみ方は人それぞれやし。まだまだ大事な場所はいっぱいあると思うので」
清水「うん、まだ隠している場所あるなあ(笑)」
――市川実日子さんと中島歩さんが演じる二人のシーンは、すごく自然な雰囲気で素敵です。
吉見「お二人とは『À Table!』で初めてお仕事をさせてもらいました。僕は何かを作った、という意識はあまりないんです。二人に最初に言ったのは、キャラクターを自分に引き寄せてほしいという話をしたぐらい。自分にないものは多分出てこないだろうし、かといって、台本の中にあるセリフとか設定の通り演じてもらっても、面白くないなと感じていて。それをいかにして、『実際に二人で喋っている』ということをやってもらうか、と考えていました。彼らはそのことについて真面目に向き合ってくれて、ものすごく台本を読んでいる」
――役に向き合っているんですね。
吉見「あくまで一役者としてそのキャラクターを演じてらっしゃる。どこまでいっても、自分ではないわけです。でも彼らは、すごく理解した上で、自分たちだったらこういうふうに考えるとか、こうするだろうなっていうことをちゃんと想像して、ちゃんと会話をする」
――その姿が自然に見える、と。
吉見「言葉のやりとりも、台本のセリフを喋るんじゃなくて、相手の言ったことを聞いていて、その次を考えて受け止めて、また喋るとか。お二人はちゃんと相手のやることも全部見てはる。ジュンとヨシヲというキャラクターとして」
――自分ではなく。
吉見「そこにちょいちょい自分が入ってきたりするんですけど、でもそういうのって、実際どういうふうに転がってくるか僕も分からへんし、こっちの方に転がしてほしいとか、ここはこういう意味合いなので、こうやってほしいとかっていうことは思わへんから、そのとき起こったことが正解だと思ってます」
(リサイズ).jpg)
――だから「作った」とはあまり思っていない、と。
吉見「彼らはちゃんと正解を出してくれはるんです。二人でやることによって、このシーンはこんなふうに見えるんやなという具体的な形になる。なおかつ思っていたのとは違うものが出てくるっていうことも、しょっちゅうある」
――ええ!?
吉見「だから、見ていて楽しいんです。僕は一番最初に身近にいる傍観者というか、観察者というか、観客というか。もちろん芝居の台本のここはキーだから、その感情よりもこっちの感情であってほしいと思うときはたまにあるから、そういうときはもう1回そこだけやり直してもらうとかはあります。でも基本的には『見せてください』というスタンスでやってるつもりなんです」
清水「いや、本当に役者さんって、毎回頭が下がるというか、尊敬しているんです。もちろん僕らは、ストーリーとかキャラクターの感情の流れを念頭にずうっと書くんです。でもどうしてもウェイトとして全体に重きを置いている。実際に台本をお渡しして読んでいただいて、演じるということは、こちらの考えていることより、ご本人の役柄の部分はきっとこちらの10倍ぐらいは考えてると感じる。あ、そうか!ここ、小さな機微の感情が繋がらないよね、とか、展開に合わせて都合よく書いていたな…とか彼らから言われて気づくことも。なので、すいません、考えが足りていませんでした!と」
吉見「よく役者さんに、謝らないでくださいって言われてます。謝ることじゃないんでって」
「具体になっちゃうから」書き込みしすぎない、独特な台本
清水「だから、よく『素で』とか言われるじゃないですか、『素の部分』とか。いやいや、素じゃなくて、やっぱりご本人が役についてとてもよく考えて演じている。ジュンやヨシヲが、このセリフのないときにどうするんだろうっていうことを考えてやっているわけで、今までご一緒した役者さん全員そうですけど、本当にその深い考察はすごい」
吉見「台本が優しくないですし。ト書きとかでいろんなことを誘導しないから」
清水「ああ、わざとあんまり丁寧に書きすぎないようにしてるかも。書き込んじゃうと具体になっちゃうから」
.jpg)
吉見「なんかの答えを見つけるための台本じゃない。台本って通常は、物事が何か起きて、それが何か感情を生んで最終的には解決していくっていうドラマを全部書いてあるもの。このチームは、そういう書き方をしないんです。だからすごく幅がある。でもキーになること、キーセンテンスは、ちゃんとはめ込まれている。そこを僕らは編んでいくというか、追いかけていく」
清水「こっちが考えていることって、たかが知れているから、役者さんにその幅で考えてもらうほうが、断然、ああなるほどって思うし。見ていて楽しい。横でお芝居を見ている感じが一番のお客さんみたいで」
吉見「テキストで書かれたものを読んで、それを肉体にするっていうことを役者さんがするわけじゃないですか」
――肉体にする、とは!?
吉見「役者さんが、台本から、物語を物理的なものとして立ち上がらせるということですね。これはすごいことだと思う。自分の体と声と動きを使って、書いてある文字を現実に起こしていくわけですから、それだけでも尊敬してしまう。そこに何か、そこはちょっと、もうちょっとニコッと笑ってとか、そこで相手を見てくださいとか、そんなん言う意味がどこにあんのかなって僕は思っています。二人は、台本から考えて、それを表現するという行為に向き合ってるから」
.jpg)
――芝居の表面的な部分を指定するのではなくて、役者さんが物語を深く理解して表現してくれれば、表面的な部分はこだわるところではないと。
吉見「こだわる必要はないんちゃうかな。二人の雰囲気と関係性がフレームの中にいる二人からにじみ出てくるので。それを補強しようとして、こういう芝居をしてくださいと言い出すと、もう嘘になっちゃう」
清水「芝居のための段取りになっちゃう」
吉見「そんなん意味がないなと思う。だから自然だと言われるのは、もしかしたらそういうところに理由があるかもしれないです。でも、自然じゃないんです。台本を演じているてるわけやから(笑)」
清水「そこが凄い。素で、とかじゃなくてものすごく考えている。逆に、書き込まれた台本に沿って演じるよりも、もっとしんどいんじゃないかなと思います。一発勝負だし、テストなしだし」
「場所も主人公の一人」現場を生かす”二人羽織”のカメラワーク
――テストは、しないんですか。
吉見「再現可能なことは意味がないと思うので、テストはしないですね。僕は場所も主人公の一人だと思っていまして、光があって、場所があって、演じる人がいる。そこでヨーイドンで始まったら、もう、その瞬間しかないと思うんです。それをもう1回って言われたら、違うものは出てくるかもしれないけど、同じものは、多分無理だと思う。今まで現場を経験してきた上で、大概テスト1回目は、おおすごい、と思うことが多い。なんで回してへんのって。フィルムで撮影していた頃は、フィルムがもったいないから、なかなか回せなかったけど、今はもうデータで収録するから、どうせやるんやったら、最初から回した方がええんちゃうか、と」
――カメラは1台ですか?
吉見「シーンにもよりますけど、基本1台です。お散歩とか、動きが座っていないものに関しては基本1台。撮影も周りに人は入れないです。カメラマンと僕と役者と録音、スチール、あともう1人、2人入れるぐらい。ほかのスタッフは遠くの方に行ってもらったりして。だから撮影現場は非常に孤独な状況になってしまう」
清水「家の中は別ですけど、ロケで実際回ってるときは、3、4人ですね。みんな遠く離れてるから。モニターで見ててもどんどん遠くに行ってしまって、電波が届かなくなってああ映らない映らないって(笑)」
吉見「僕はモニターも見ないです。普通はベースっていう場所が作られて、そこにみんな集まって、テストとか、本番いこかってやるんですけど、そういうことは一切ないですね」
――じゃあ、どちらに?
吉見「カメラマンの横にいます。カメラマンを引っ張ったりするし」
清水「ベルトを持って引っ張ったりもして、まるで二人羽織だよね(笑)」
――(笑)すごいですね!
吉見「カメラが回っていても、芝居の途中で、回しておいてもらって中に入って、ちょっと二人と話をして、フレームから出て、また回し始めたりとか」
(リサイズ).jpg)
(リサイズ).jpg)
清水「芝居に合わせて、カメラがぐーッと入り込むのはあんまり好きじゃないよね。芝居で見せる場面になると、カメラマンってぐーッと入ろうとするんだけど、逆に引け引けって」
――引くカットは、印象に残っています。「~ノスタルジックな休日~」の11話で、圭子おばさんから「あなたたち夫婦にこの家を貸そうと思ったのよ」って言われるシーンで、重要な対話のシーンだけどカメラは引いていく。それは家についての会話だったからなのでしょうか?
吉見「そういう意図です。カメラワークで意味を持たせようと考えてました。二人に歴史があるように、家にも歴史があるっていうか。二人を結ぶものとして家を見せたかった。だからカメラを止めたくないんです。舞台も主人公なんで」
.jpg)
「撮ってると、だんだん関係なくなる」カット割りはあくまで想定。構図、色味にもこだわる
――カット割りはされるんですよね。
吉見「自分の台本に、場所を想定して、ここはこう、次はこんなショットかな、みたいなカット割りの作業は一応やります。でも、撮ってると、だんだん関係なくなる」
――現場でずいぶん変わる、と。
吉見「変わるっていうか、現場は生やし。台本に線を引っ張ってるのは想定やし、さっきもお話ししたように、場所という主人公がいる、光があって、演じる役者さんがいて、もう三つも違う要素があるから、計算できない。行ってみて考えて、一番ベストなのは何んなんか、と思うと、カメラを止めてる場合ちゃうやろ、と。僕はよく、そう思うんだけど、役者さんはもしかしたら違うかもしれない(笑)、なかなかカット掛かからないな、ここまでって言ったじゃんって(笑)」
――(笑)。画作りという流れで伺いたいのが、画面の構図がすごく特徴的で素敵です。今のお話ですと、現場に行ってから、切り取る構図を決めるのですか?
吉見「あ、そうですね。細かく考えて話をして、カメラマンがつけてるレンズのミリ数が違ったら変えてもらったりもします。ドラマ的にオーソドックスなレンズの選び方っていうものがあるんですけど、例えば、いすに座っているときに、足元を切るのがセオリー。でも僕は、足元の床まで入るようにしたいから、それが撮れるようにレンズを変えて何ミリにしてほしいとか。もしかしたら、特徴的に見えるんは、普通は使わないレンズを使っているだけの話かもしれないですね」
清水「ワイドは好きだよね、普通は大体35mmで撮るところでも、ワイドの18mmで撮ると、かなりカメラの位置が演じる人の近くに来るんですよね。35mmと18mmだと、人物を同じ大きさで入れたとしても、見え方は全然変わってくる」
――レンズの違いというのは大きいのかもしれないですね。
吉見「大きいと思う。あとは、編集の段階で行う色みの調整ですね。グレーディングというんですけど、清水さんが、こだわりがあるんです。現実の日常の景色を撮っているんだけど、そこにひとつバイアスがかかって、ちょっと、まぼろしというかフィクションのようなニュアンスが足されてる」
.jpg)
清水「1960年代のフランス映画の、何となくちょっとイエローがかかってる感じね」
吉見「最初の『ちょこっと京都~』で、どんな感じがいいんかなって話していたときに、これは60年代ではないんだけど『髪結いの亭主』(’90年/フランス)っていう映画の感じかなと二人で意見が一致して。ちょっと色味の強い、強いっていうのは、ビビッドじゃなくて、脱色しているけど色がにじんでいるような感じが清水さんも僕も好きなので、それを意識しながら撮りました」
清水「『名建築~』からなんとなく色味の形が決まってきたかな。スチールの廣田(美緒)さんにもいろいろアイデアを出してもらってね。いつもかなり色はいじってる…。昔のヨーロッパ映画的な感じはお互い好きだしね」
――色味もこだわって。
清水「『名建築~』のときは、オールドレンズも使いました。カメラマンの水口(智之)さんが考えてくれて。80年代の、古いレンズです」
吉見「エエ感じになるんです」
清水「古くて甘い感じ」
吉見「今は、画素数が上がってデータ量が増えて」
清水「画面がパキパキしていますけど、そういうのとは逆の」
吉見「天邪鬼なんですよ。そうじゃないことがエエなっていう話をして」
特別な事件は起きない。友達の夫婦を見ているような日常の話
――映像のニュアンスもそうですけど、最近は動画配信サイトが一般的になってきて、ドラマの本数がふえ、内容も刺激的な題材のドラマが多い中で、いい意味で異彩を放っているように思います。今回の「暮しの手帖」も。
清水「大好きなんです。日曜日の夕方に読むのが至福で。エプロンメモとか。読者の欄で結構泣いちゃったりするぐらい良い話があったりして、個人的に大好きで」
――ジュンもずうっと、編み物をしていますよね。
清水「そう、最近編み物を自分も勉強したいと思ってます(笑)。『暮しの手帖』の話になっちゃうんですけど、絶対広告も取らない主義だから、ドラマ化は難しいだろうと思っていたんです。でも勇気を振り絞って打診してみたら、スタッフの皆さんの中で「À Table!」を見てくださっている方が結構いらして、やった方がいいんじゃないかって。もう、やった!って感じで。もう一方的に、僕が『暮しの手帖』が好きなので」
.jpg)
――好きが最初にあって。
清水「花森安治さんが好きなんですよね、考え方とか。僕ら子どもの頃って、することないから、結構、家にあると読んだんです。だから、今回、バックナンバーを読んだら、そこに紐づいて、あの頃の実家の部屋とか、アラジンのストーブとか、こたつの網目だとか、記憶がわーっと出てくる。やっぱりすごい雑誌だなと」
――圭子おばさんが作ってくれた「うにごはん」を食べたヨシヲが、実は子どもの頃によく食べていたことをだんだんと思い出すシーンがありましたけど、まさにそれですね。
清水「そうそう、そこは横幕さんのアイデア! 先ほど刺激的なドラマが多くてっていう話題がありましたけど、『À Table!』は、横幕さんと二人で事件を入れずにつくるっていうのを課したから、毎回ものすごくしんどかったんです」
――自分たちで縛りを。
清水「だから、より日常っぽいというか、人のうちに遊びに来ているみたいってよく言われるんです。友達の夫婦を見ているみたい、と。何回も見てほしいし、長く愛してもらいたい。『À Table!』は、何回か見ると目線が変わって、いろいろ発見があると、皆さんおっしゃってくれるんです。そういう要素は何となく混ぜ込んであるので」
――1回見ただけでは気づかないところがたくさんあると思います。
清水「回想シーンは入れないとか、夫婦の間でも相手を慮ってなかなかその場で質問しないとか、あんまり説明的になりすぎないようにはしてるかな。でももう1回見たら、何となく『ああそうか』と感情の流れ分かってくるっていうか。そんなスルメみたいなドラマは目指しています」
吉見「答えは出さないっていうことちゃうかな。答えはないですから。それは日常だと思うんで」
清水「日常はそんなに事件起きないし」
普段見聞きした出来事を盛り込んでいるから、ドラマのために作っている感じがしない
――日常といえば、ヨシヲが、台所のルールは全部ジュンの基準に合わせている、とか、時間を戻すとしたらジュンの実家に挨拶に行ったときに噛んで「ふぁじめまして」って言ってしまった場面をやり直したいとか、共感できる日常の話が、これでもかというほど詰まっています。
清水「身近な話は、普段からあったことをたくさんメモに書いています。いつも散歩して、メモに残して、意識はしていますね。(『名建築で昼食を 大阪編』の)挨拶しない男とかも、自分の経験です」
吉見「清水さんは、よくそんなん思いつくなっていう、ちょっとした日常の些細な事柄にアンテナを張ってはります」
清水「そこは横幕さんと二人で、自分たちの身近な話で作るよね。こんな話あんな話って何となくネタを伝えておくと、逆に横幕さんご自身のネタも入って、たくさん持ち寄れるので、すごくいいのかも」
吉見「嘘がない。ドラマのために作ってる感じがしない。それが見てる人にはしっくりくるんちゃうかな」
(リサイズ).jpg)
清水「何かにも書いた話なんですけど、若い人との会話の中で『負けて勝つ』という言葉を使った時に、なんですかそれって言われたことがありまして、結構ショックだったんです。『負けちゃ駄目じゃないですか』って言われて言い返せず、もごもごしちゃって。なんかそういう日本人が昔、みんな共通に持ってたような感覚が共通している夫婦って、見ていて幸せだよな、と思ったりしてね。そういうのを軸にした物語にしたいと思ったのが、『À Table!』の原動力かなぁ。自分が見たいなと。例えば、夫婦に絡む登場人物も、突飛な価値観の人を登場させて物語を展開させるんじゃなくて、『優しいという価値観』は一緒だけど『優しさ』の見方や考え方が少し違っている人とかね」
――ジュンとヨシヲの夫婦の絆は、すごく強く感じます。
清水「理想の夫婦とか仲がいいとか言われているんだけど、一応自分たちの中では、若い頃の二人は喧嘩も当然しているだろうし、トラブっているだろうと考えてます。それが当然だと思うんですよね。歳を取ると喧嘩する体力もないので。これ言うと怒るな、というのが分かってきて、そこは言わないとか。同じ文学が好きでも、同じ系譜のものは全然読まずにきたとか。お互い知らないものを知れるっていうか、好きなものは一緒だけど、深掘りしているところが違う。そういうふうには作っているつもりなんです。ちょこちょこ作家の名前を出したりしているのは、そういうキャラクター付けをしているからでしょうね」
吉見「でも解決はせえへんっていうね」
何度も見ると、あらためて気付くことがあるスルメのようなドラマ
――いよいよ配信が広く始まります。何度でも見てほしいですね。
清水「シーズン2を見ると、またシーズン1の『~歴史のレシピを作ってたべる~』に戻りたくなったりしていただけたらありがたいなと。ああ、あれのときってどうだったっけ、と思うんですけど、そこも説明してないし。見直すと、ああそうかって思えるようにしてるかも」
(リサイズ).jpg)
――そういう意味では尺も30分で短くまとまっているので、見やすいと思います。そしてこのドラマは、この先も続けられますよね。まだまだジュンとヨシヲの話を見たいです。
清水「その歳その歳でまた感じ方が違うので、面白いものです。皆さん歳を経ると、変わっていくので。一からストーリーをいろいろ考えている時期ってもう鰹節が削れていく感じ。だから現場に入って、監督が苦しんでいるともう嬉しくて嬉しくて(笑)、こっちが苦しんでいるときには、嬉しそうな顔をするので、逆に現場で苦しんでいると、よしよし、苦しめって(笑)」
――(笑)お二人の空気感がとっても素敵です。
二人「いや、本当にありがたい」
<後編に続く>
.jpg)
■Profile
清水啓太郎(しみず・けいたろう)
1968年生まれ。岡山県出身。松竹撮影所企画部。テレビドラマのほか、多くの映画のプロデューサーを務める。主な作品は、「ミスター・ルーキー」(’02年)、「天国はまだ遠く」(’08年)、「焼肉ドラゴン」(’18年)、「お前の罪を自白しろ」(’23年)など。24年にアメリカで放送された真田広之主演「SHOGUN」ではコンサルタントを務めた。
吉見拓真(よしみ・たくま)
1965年3月20日生まれ。大阪府出身。ポン・ジュノ、ジョン・ウー、マーティン・スコセッシ等の海外監督作品や中島哲也・三池崇史等の国内監督作品に助監督として多数参加。監督作品は「たべるダケ」(’13年/テレビ東京)、「ちょこっと京都に住んでみた。」(’19年、’22年/テレビ大阪)、配信ドラマ「ネット興亡記」(’20年/Paravi)、「名建築で昼食を」シリーズ(’20年、’22年/テレビ大阪)、「À Table!」シリーズ(’23年、’24年/BS松竹東急)、「京都のお引越し」(’23年/ABCテレビ)。
.jpg)
「À Table!~ノスタルジックな休日~」 配信情報
U-NEXT、Lemino、Amazon Prime Video、Hulu、DMM TV にて配信中
(2024年12月20日(金)より配信開始)
■関連記事
取材・文/三宅俊郎