42回の歴史の中で初めて受賞候補者を発表し注目を集めた2023年度の向田邦子賞の受賞者が、NHKBSプレミアムで放送された「グレースの履歴」の脚本を執筆した源孝志さんに決定しました! TVガイドみんなドラマでは、週刊TVガイドと共同で源さんに受賞の喜びとともに、対象作品となった「グレースの履歴」を執筆される中での思いや、脚本家としてだけでなく共に監督・演出としても評価の高い源さんならではの、創作の舞台裏のお話をたっぷり伺いました!
ノミネート作品に自分も好きで見ていた作品もあり、これは取れないだろうなあと思っていました(笑)
――向田邦子賞について、源さんはどんな印象をお持ちでしたか?
「子どものころから向田さんが書かれたドラマをテレビで見ていましたし、やはり向田邦子賞は憧れでした。もちろん、欲しいとは思っていました。今回自分がノミネートされたことは聞かされていたんですね。僕は『サンクチュアリ-聖域-』も好きで見ていたし、ヨーロッパ企画の上田誠さんの作品も、あのナンセンス感が大好きで(笑)、舞台をよく見て行っていました。そういう候補者の方たちがいらしたので、まぁ自分はもらえないかなって思っていたんです」
――受賞されたと聞いた時は、どんなお気持ちでした?
「ただただありがたいです。何も言うことはありません」

映像化をイメージして原作小説を書きましたが、今回の脚本では、実際に演じる役者さんに当てて書き直しました
――源さんは、演出家のイメージが強く、一つの作品で脚本・演出の両方を担当されるケースが多いですよね。
「多分この業界内で、僕=脚本・演出のイメージがあるんでしょう。僕に来る仕事は当然『脚本・演出で』と思われている気がします。ただ僕にとって脚本はすごく大事で、毎回一生懸命書いているので、『もっと脚本家として認てくれないかなぁ』という思いは何十年も持ち続けていました。脚本だけの仕事も来てほしいんですよ。あちこちで『脚本だけの仕事、全然やりますよ』って言っていたんだけど、来ないですねぇ。『そんなこと言っても、結局自分で撮りたいような脚本を書くんだろう』なんて思われていたのかもしれません」
――源さんが脚本を書かれる時のこだわりはありますか?
「僕は細かく厳密に書きます。初めて仕事をする役者さんから『もっと‟ざっくり”した本かと思ってました』ってよく言われます。‟ざっくり”っていうのは、現場で監督としての自分がアレンジを加えやすいような、余白の多い本のことかなと思いますけど。でも、その逆で、僕はト書きなどもできるだけ具体的に書くんです。ト書きというより描写ですね。脚本というのはスタッフと役者しか読まないものですが、共通の世界観を持ってもらいつつも、読み物として面白く書こうという気持ちはすごく持っています」
――今回はご自身の書かれた原作小説があって、そこから脚本を書かれたんですよね。原作から脚本にする段階で、特に手を加えたことはありますか?
「これは演出家としての私の悪い癖ですが、小説を書く時にも『このキャラクターを誰に演らせるか』ってことをついつい考えちゃう。いわゆる‟当て書き”ですね。十数年前、あの長い原作小説を書いている時も、とある役者をイメージして書いていました。そのほうが執筆するモチベーションが持続するんです。それからずいぶん時が経ち、今から3年前にドラマ化しようという話になって、主人公の蓮見希久夫を滝藤賢一さんにやってもらおうと決まりました。小説を書いていた時の希久夫のイメージとはちょっと違う俳優ですが、このドラマは彼に任せたいと直感的に思った。しかし滝藤さんが希久夫を演じるとしたら、原作とのズレも出てくるので、脚本は滝藤賢一に寄せて随分書き直しました。ヒロインの美奈子も尾野真千子さんに決まってから、彼女に当てて書き直しました。立ち居振る舞いとか、怒り方とか。やっぱり役者に寄せた方が、キャラクターの魅力が出るんですよね。『役者はどんな人間でも演じられなきゃいけない』というのは、僕はナンセンスだと思っていて。やっぱりその役者が持っている魅力と、演じる役のキャラクターが近いほうが良いと思うんです」

――希久夫、美奈子以外の人物のセリフも、演じる役者さんに合わせて直したのですか?
「もちろんそうです。また林遣都さんの演じた羽田純哉や、木村祐一さんに演じてもらった、羽田の腹違いの兄貴の役は、小説には全然登場しません。あの辺は、ドラマの脚本を書く時に新たに着想したキャラです。主人公が車で旅していろんな人間に会っていくうちに、彼自身のキャラクターもどんどん変わっていきますが、その途中で、ああいう‟異物”のような存在と出会って、何らかのつながりを持って別れていく、というのがロードムービーの良さかなと思いますね」
――脚本と監督を兼務されることで、今回特にご苦労なさったことは?
「連ドラの場合は一人の演出家だと撮りきれないので、大体チーフの演出家が4~5本撮って、あとは3人ぐらい若手の演出家が撮るパターンが多いんです。僕も今回クランクインまでに脚本が全部上がりそうにないなと思って、信用に足る、僕の好みをよく知る演出家に3、4話を撮ってもらいました。すごくよく撮ってくれたと思います。特に3話は泣けた。満足はしてるんですけど…やっぱり自分で撮りたかったなぁと(笑)。勝手なもので、そういう風に思っちゃうんですよ。だから、次に連ドラを撮る機会があれば、どんなに苦しくても自分で全部撮ろうと思いました。その方が、悔いが残らないから」
大変だったのは状態の良い、左ハンドルのホンダS800を探すこと。土壇場で見つかり、役者さんたちにも運転してもらいました
――本編では美しい映像も印象的でした。特に、赤いS800が走るシーンはこのドラマの肝ですよね。
「そうですね。あの車を探すのは大変だったんです。やっと見つけたのがクランクインの2カ月前、細かい整備を終えて我々の手元に来たのが1カ月前というギリギリのタイミングでした。あれが見つからなかったらピンチでした。赤色がなかなかなくて『色、変えませんか?』なんて言われたけど、無理を言って探してもらいました。左ハンドルのタイプも何台かあったんですが、シートやステアリングの状態が良くないとかね。諦めかけたギリギリの時に、あのピカピカの赤い左ハンドルのS800が見つかったというわけです。1967年製、アメリカ統治下の沖縄で車好きの米軍関係者が乗っていたエスハチで、’72年の沖縄返還の時に売却され、九州の中古車屋さんにやってきた。それをまた日本人の車好きの方が購入し、50年も大事に乗ってきた、わずか2オーナーの掘り出し物です。何よりエンジンの調子がすごく良くて、大切に乗られてきたことが分かった。やっぱり実際に走るシーンを撮りますからね。今回S800を運転する滝藤さん、尾野さん、劇中でS800を直してくれるバイク店主の仁科を演じた宇崎(竜童)さんには、かなり練習してもらいました。最終的には滝藤さんはあの厄介なマニュアル車の運転がものすごく上手くなったし、尾野さんは最初から上手かったです。彼女は元々車好きで『昔、面倒くさい車に乗ってたから』って言っていました。今回は極力役者本人に運転してもらっていて、牽引はほとんどしてないです。運転しながら芝居をするのは危険なので牽引撮影をするんですが、自走にこだわったので、キャストが運転しているシーンはセリフを無くしました。走ってきて止まって泣くとか、泣きながら乗ってバーっと走り出すとか、もちろん安全確保は十分にした上で、全部役者本人に車を走らせてもらいました」

――4話のグレイス・ケリーの回では、ホンダという会社の歴史的な話がたくさん登場しましたが、あのエピソードはどう発想されたのですか?
「あの話は原作小説にもあるんですよ。原作小説は各章立てで、各章の主人公はほぼ希久夫か美奈子なんですけど、1章だけ、征二郎というメカニックが主人公の章があります。本田宗一郎さんがまだ現場に出ている頃に入社した若いメカニックですね。その章は、随分ホンダから社史をお借りして書きました。それで小説を出す時に『これ、大丈夫ですか?』とホンダの広報さんにはお伺いをたて、本田宗一郎さんのご遺族や、いろんな方からの許諾もいただいたのを覚えています」
――ドラマでは、風景の美しさも印象的でしたね。
「今作はドラマの舞台がどんどん変わっていくロードムービーの形になっていますが、『自分たちの住んでいる街っていいな』と思ってもらえるように、日本各地の美しい風景を一生懸命撮りましたね。たとえば、信州の北アルプスの麓の田園で、S800がオーバーヒートしちゃうシーンがあります。あの背景に北アルプスが見える美しい田んぼでの撮影は9月下旬の予定だったんですけど、『早く撮影しないと、刈り取っちゃうよ』と言われ、無理して撮影順を3週間くらい前に持ってきたんです。そのように撮影順を調整したりして、できるだけ美しい日本の風景を撮ろうとしていましたね。天気待ちもずいぶんしました。長年僕の作品で撮影を務めるカメラマンでさえ「監督、とことん待つんはええんですけど、撮りきれませんわ」と何度も愚痴を言われました。『叙情的』という言葉がありますが、やっぱりちょっと気持ちが動かされるような風景の中じゃないと、叙情的なドラマって撮れないんですよね。雲を割る一瞬の陽差し、草を揺らす風、そういうのはVFXとかじゃできませんから。本来、連ドラはコンパクトに撮らないとダメなんですが、今回は腹を括ってスケジュール的にもゆったり撮っていました」
――視聴者の方からたくさんの反響があったと思いますが、映像の美しさを支持する声も多かったですよね。
「そうですね。美しい風景を見てくださった方から『もう十何年も帰っていない故郷に帰ろうと思いました』『墓参りで実家に帰った時に、田舎の道をちょっと散歩しました』『小さい頃に行った海水浴場に行きました』といったコメントやお手紙をたくさんいただきました。それはすごくうれしかったです」

美奈子と草織の対峙は、尾野さんと広末さんのおかげでリアリティーを持ったシーンに
――他に、撮影で特に印象に残ったエピソードはありますか?
「最終話の美奈子と草織(広末涼子)が対峙するシーンですかね。僕が懸念していたのは、特に原作小説を読んだ女性の方から『美奈子のような気持ちには全然なれない』というお声が結構ありまして。病気をなんとか自分一人で克服しようとしているのはまだいいけど、夫の昔の恋人に会いに行って、その人に夫を委ねるというのはどうなんだろうと。人は自分がもうすぐ死ぬというリアルな切迫感があると、そういう飛躍をすることもあるんじゃないか、と僕は思っていたんですけどね。クランクイン前に広末さんと話した際、『一生懸命演じますが、個人的にはこの気持ちは理解できません』と言われたんです。ズバッとそう言ってもらう方がいいんですけどね。懸念の顕在化です。だから『無理に分かろうとしないで結構です。違和感があるセリフは、話し合って直しましょう』と言いました。これは脚本・演出の両方をやっていることのメリットですよね。今のドラマは欧米も日本もプロデューサーシステムで、主にプロデューサーと脚本家が作り上げた脚本が、ある種『契約書』めいた力を持っている。脚本家の方が巨匠だと、現場で監督や役者が臨機応変に変更できない不自由さもある。難しい問題ですが、作・演出であれば、幾分かは撮影現場で表現の自由度が担保される気はしています。僕は自分の書いた脚本が100 %正解だとは思っていません。もちろん考え抜いて書いているし、スタッフの意見も充分聞いて決定稿にしているわけですが、最終表現者である役者が『気持ちとして自分の中に落ちてこない』、あるいは『どんな気持ちでこのセリフを言ったらいいのか?』ということも当然ある。そんな時はコミュニケーションがとても大事です」
――実際、あのシーンはとても見応えがありましたね。
「感情的に激しいシーンだから何回も撮れないと思ったけど、3回戦くらいやりましたかね。セッティングが終わって、軽くテストをしたんですけど、そこで尾野さんはもう勘弁してほしいくらい泣くんですよ。『いやいや、テストだから。エネルギーやパッションは本番にとっておこうよ』と言ったんだけど、毎回テストで泣くから、途中でテストをやめた記憶があります。だいたい、前日にホテルで脚本を読み直している時から号泣していたそうで、朝現場に入ってきた時に目が腫れているわけですよ。あの人は芝居を技術とか理屈とかでやっていない。もう完全に美奈子というキャラクターと同化しているわけです。そういう尾野さんの本能的なエモーションが、広末さんの芝居に影響を与えないわけがない。最終的には『予想外のところで気持ちが動いてしまいました』って。2人のお陰で、あのシーンにすごくリアリティーを持たせることができました。嘘臭くないんですね。大したものです。あの日は朝から撮影を始めて午後3時ぐらいで終わったけど、彼女たちはヘトヘトでしたね。良いシーンが撮れたからこっちも気分良くて、ちょっと(飲みに)行きたいくらいでしたが、2人ともそんな余力もなく、結局滝藤さんと二人で飲みました(笑)」

今後もいろいろアイデアがあるので、順番に、丁寧に、取り組んでいきます
――すごいエピソードですね。では、今後こんな物語を書きたいという構想があれば教えていただけますか?
「ありますけど…詳しくは言えません(笑)。言える範囲では…次の連ドラも予定されていて、今脚本を書いているところです。それも今時珍しくほとんど地方ロケで、自分で全部監督をやるつもりです。その次に書く小説ももちろんドラマ、映画にしようと思っていて…それは、一言で言えばサスペンスですね。なんかサスペンスをやってみたくて。これは僕が監督しなくてもいいです。僕の原作を韓国の脚本家が書いて、韓国の監督に撮ってほしい。韓国映画が好きなので、そんな構想も持っています。それと恋愛ものも撮ってみたいですね」
――恋愛ものですか! ちょっと毛色が違うように思えます。
「40代の初めの頃、江國香織さんの小説で映画を撮ってヒットした影響なのか、恋愛ものの仕事しか来なかった時期がありまして、ちょっと誤解されているのかな、と思っていたこともあったんです。でも今、僕は60歳を過ぎましたが、この辺で大人の純愛ものをやってもいいかなと。ヒロインは30代、相手の男は還暦過ぎた脚本家のおっさん、とか。来年、久々に映画で時代劇を撮る予定ですが、それはすごく原作が面白くて、すいすい脚本が書けました。『痛快娯楽』です。ご期待ください!」
――伺っていると、かなりの仕事量ですね。これからも頑張ってください!
「そうですね。とにかくいろいろやりたいことはあるので、順番に、丁寧にやっていかなきゃいけないなと思っています」

■プロフィール
源孝志(みなもと・たかし)
1961年6月5日生まれ。岡山県出身。’84年、ホリプロ入社。’86年、日本テレビに出向。主にバラエティー番組のプロデューサー、ディレクターとして活躍後、‘03に独立して株式会社オッティモを設立。これまで手掛けたドラマ作品は、「京都人の密かな楽しみ」(’15年)、「スローな武士にしてくれ~京都 撮影所ラプソディー~」(’19年)、「令和元年版 怪談牡丹灯籠」(’19年/ここまでNHK BSプレミアム)、「ライジング若冲 天才 かく覚醒せり」(’21年/NHK総合)、「忠臣蔵狂詩曲No.5 中村仲蔵 出世階段」(’21年/NHK BSプレミアム)など。多くのテレビドラマ作品では演出も手がけるほか、映画「東京タワー Tokyo Tower」「大停電の夜に」(ともに’05年)などの監督も務めている。

「グレースの履歴」情報
NHK BSプレミアム
2023年3月19日~5月7日放送
原作・脚本:源孝志
演出:源孝志、西山太郎
出演:滝藤賢一、尾野真千子、伊藤英明、柄本佑、林遣都、山崎紘菜、黒谷友香、宇崎竜童、広末涼子 ほか
撮影/蓮尾美智子
取材・文/水野幸則

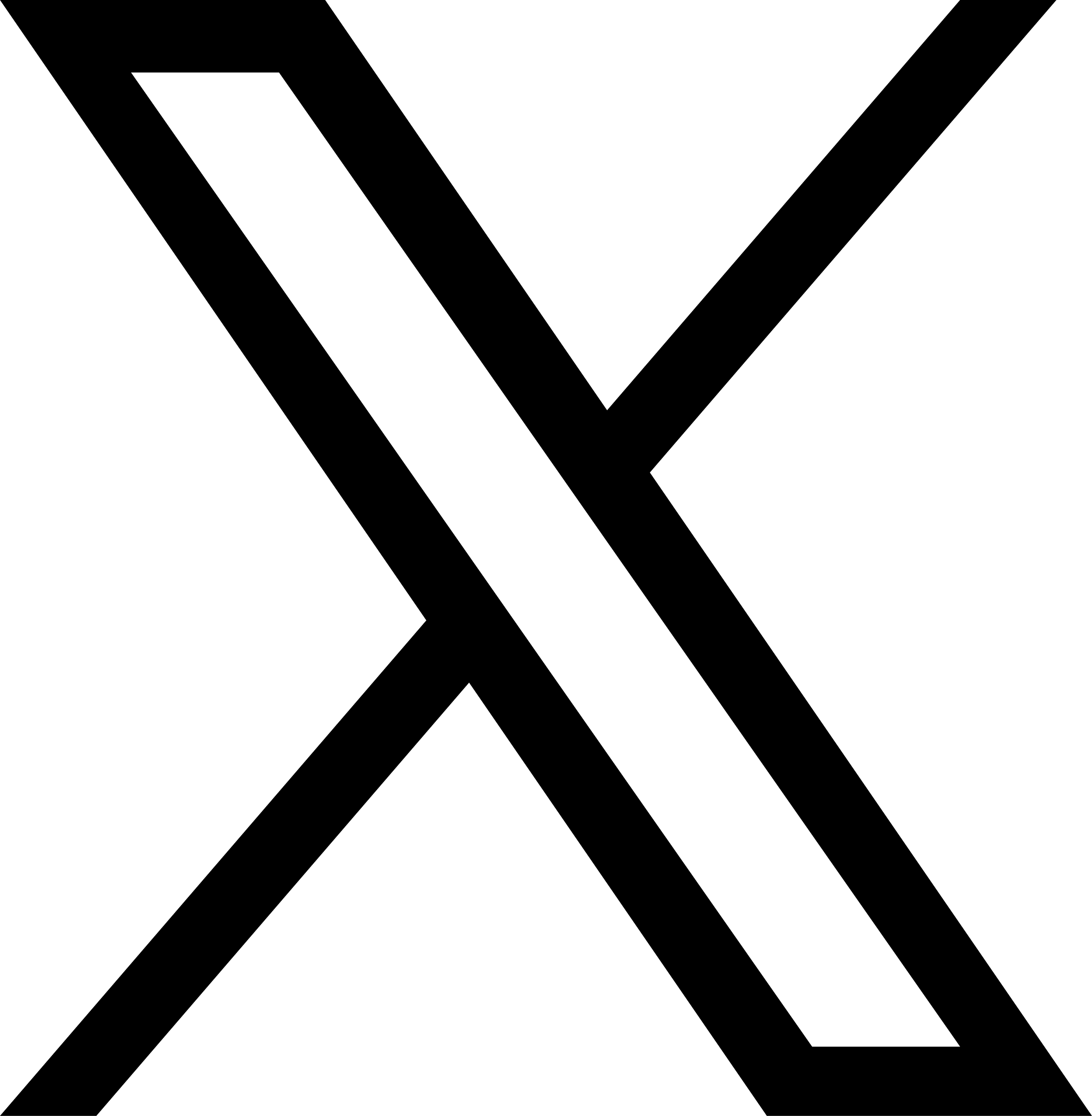


サムネ-4.jpg)