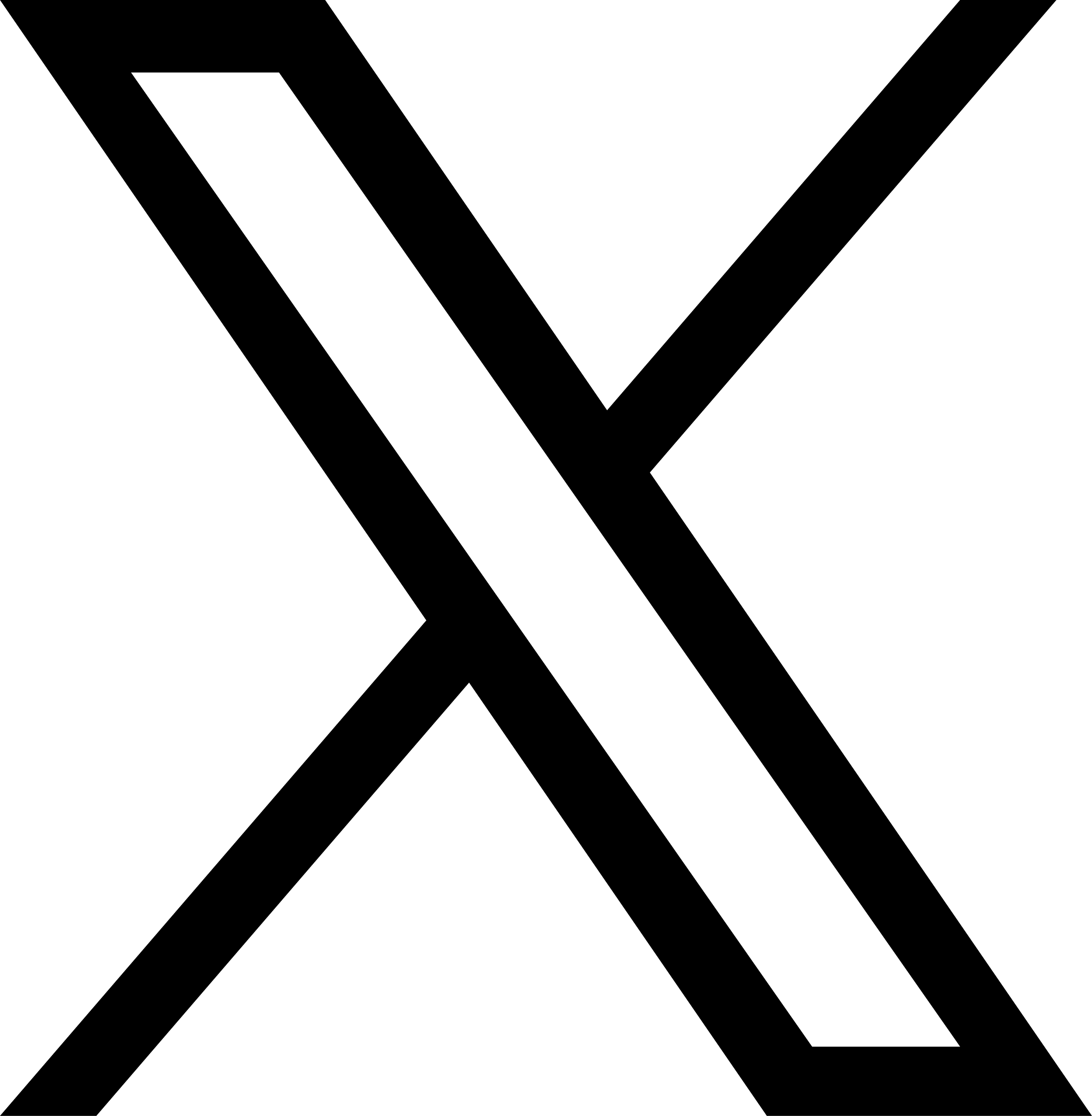小劇団を舞台に怪奇現象を機に繰り広げられる若き劇団員と主宰者の人間模様を描く「OTHELLO」。本作を書き下ろしたホラーの名手鈴木光司さんにインタビュー!
1990年代に「リング」「らせん」でジャパニーズホラーの火付け役となった鈴木さんに、作品の見どころを交えながら、ホラー克服法も伺いました。
僕は、昔からホラー映画はまず見ない(笑)
――鈴木先生は「リング」をはじめとした作品でジャパニーズ・ホラーの火付け役と言われていますが、もともとホラー作品がお好きなんですか?
「僕は、昔からホラー映画はまず見ない(笑)。頭の回路が完全に理系で、ホラーは非科学の代表ですからね。科学的に説明がつかないような現象というのは実際にいっぱいありますけど、ホラーを見ても僕は全然怖くないんです。だから、最初はホラーを書くつもりもまったくなかった(笑)」
――それは意外です! だからこそ、独創的な作品が生まれたんでしょうね。では、先生はホラー作品をどのように捉えていらっしゃるのでしょうか。
「僕はよくジェットコースターに例えるんだけれども、傾斜角があればあるほど、みんな怖くてキャーキャーと叫んで、降りる時にはみんな笑っているんですよ。振れ幅の大きな怖い体験をすると、みんな笑うんです。僕がいつでも望んでいるのはそういうイメージ。見終わった時に暗くなるんじゃなくて、開放的な気分になるもの。ハリウッド版の『ザ・リング』が作られた時に、現地で観客の入った試写会に行ったんですよ。その時にお客さんを見ていたら、怖いシーンがあると飛び上がって驚くわけ。そして、そのあとに笑っているんです。その心理はおそらく、怖いシーンで驚いてオーバーアクションしてしまった自分に笑っているんだよね。日本では、観客は映画を静かに見るんだけれども、アメリカでは拍手したり笑ったりと自由。また、みんな帰っていく時の顔が非常に明るくて満足げで良かったんですよ。その反応を見たプロデューサーが全米ロードショーの館数を大幅に増やして、大成功を収めたんです。心底お客さんを楽しませるのは一番難しいことだけど、見終わったあとに笑顔になれることは絶対に大事だと思います」

克明な描写により、映像の中で起きている出来事を現実のように錯覚させる
――ホラーを克服するための準備として「ホラーの方程式」を紐解いていければと思うのですが、そもそも、なぜ人はホラー作品を怖がると思われますか?
「サイン会をやったりすると『先生すみません。私、怖いものは苦手で見ていないんです』という方がすごく多いんです。そういう人にどんなイメージを持っているのか聞くと、血がドバーッと出たり、残虐なシーンがあったりという話が出る。でも僕は、自分の原作がホラー映画になる際に監督に必ず注文するのは『血は一滴も出すな』『幽霊を出すな』ということなんです」
――あの…貞子って幽霊じゃないんですか?
「あれは幽霊(笑)。僕のリクエストは、驚かせるための常套(じょうとう)手段として幽霊を出さないということですね。そういう制約があるから、アイデアが出てくるんですよ。貞子も、その制約の中でいろいろと考えて、テレビから出てくるというアイデアが浮かんだんです。ちなみにハリウッド版でも同じリクエストをしたんですが、幽霊が出るわ、出るわ(笑)」
――外国のホラー映画は、血も残虐なシーンも多いイメージです。
「そうそう。ジェイソンが斧を持って出てきたりね。怖いものがそのまま出てくるでしょう。そうするとホラーというよりアクションになっちゃうんですよ。ジャパニーズ・ホラーは、怖いものそのものは出ないんだけど、見えないからこそ正体が分からない怖さというのがあるんです」

――たしかに「正体が分からない」というのは一番の恐怖です。
「それから、物語の舞台や設定も大事です。例えば、火星を舞台にして怖い出来事が起こっても、そんなに怖くはないんですよ。なぜかというと、火星で起こったことは自分とは無関係だと思うから。ホラーというのは、怖いことが起こるのにふさわしい場所を作らないといけない。それにはまず、自分と距離が近い場所。それから暗い場所であって、狭い場所。逃げ場がない場所ですね。そして水気がたっぷりの場所。そこで僕が『リング』で考えたのが井戸だったんです。さらに『リング』の場合、“このビデオを見た人間は1週間後に不審な死を遂げる”という設定がある。小説の中で僕は、ビデオに映る映像を克明に描写したんです。すると読んだ人間は映像が頭に浮かんで、ビデオを見てしまったと錯覚する」

――物語が自分ごとになった途端、怖さが倍増するんですね。
「そう。他人ごとだったら怖くない。だから自分ごとに持っていくこと。これが僕の編み出したホラーの王道です。本当に怖い物語というのは、精神的にじわじわくる。そういったシチュエーションや構造をいかに作れるのかというのが大事なんです。その中の表現方法として、血や幽霊をそのまま出しちゃったら台なしになっちゃうんですよ」
ホラー克服法は、怖さの向こうの希望を信じること!
――人が恐怖を感じる仕組みはよく分かりました。次は、怖がりな人がホラーを克服するためのヒントをいただきたいです。まず、怖がりの人は物語の中で「ちょっと見てくる」と言って出て行った人が殺害されたり、犯人らしい人を最初に疑った人が殺害されたりと、何かが起りそうな「予兆」が、苦手です。
「僕の作品に関して言えば、そういう『あるある』は絶対にやらないです。ホラー関係なく、ありがちなシチュエーションのものは作らない。それに、先ほども言ったように血や幽霊も基本的に出てこないですから、そこは安心してください」
――なるほど。とはいえ、つい先を想像して怖くなってしまうんです…。
「怖がりの人は、想像力が豊かなんでしょうね。それはとても良いことですよ。ホラーというのは想像力を駆使して作られている。僕は、読者の想像力に火をつけてやろうと思って書いているんですよ。だから、そういうシーンの文章は緻密になる。緻密に描写することで、匂いや風を感じたり、本当に居るわけではないんだけど、読んでいる人のうしろに誰かが居るかもしれないと思わせる。一人一人の想像力に訴えかけているんです」
――たしかに勝手に想像して怖くなってしまい、最後まで見られないのが残念です。
「僕は、怖いまま放り出さない。必ず最後は明るい未来を予感させます。『リング』や『らせん』のシリーズにおいても、最後まで見ると希望の物語なんです。だから僕を信じて最後まで見てほしいですね」
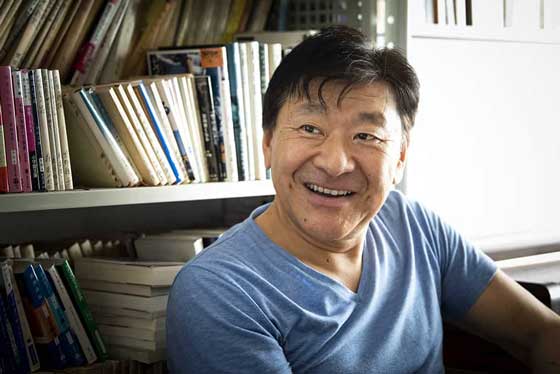
――途中でやめるから怖いまま、ということですか! 先ほどお話に出たジェットコースターも、落ちる時よりも昇っていく時のほうが怖いですもんね。
「そうでしょう? で、最後は笑っている。僕も子どもの頃、注射を受ける日は、並んでいる時が一番怖かった(笑)。人は、何かを待っている間のほうが怖いんですよ。でも、最後はすっきりするから」
――怖さを感じるのは自分の想像力が豊かな証拠だから良いことだと思って、先には良いことがあるから乗り越えてみようとことですね。少なくとも先生の作品には、希望がある。
「そうそう。人を怖がらせて不安にするタイプと、自分の力を分け与えるタイプがいるとしたら、僕は確実に後者だから」

「OTHELLO」は、僕の劇団経験がベースになっている
――無事、ホラー克服のヒントを教えていただけましたので、ここからは安心して(笑)、現在放送中の鈴木先生の最新作「OTHELLO」の見どころをお聞きします。今回のアイデアはどこから生まれたんでしょうか。
「企画を立てたのは去年で、当時、僕は放送される頃にはコロナが終息していると判断したんです。だから、自粛が明けてもっと明るくなろうという希望があった。僕に求められるものはホラー的なものでしょう。その中で、作品を作るにあたって自分に要求しているのは独創性です。そこで今回は、ホラーの色合いを入れながらコメディーの要素を入れました。なおかつ劇団が舞台で、ダンスの入ったミュージカル要素もある。それによって、怖がって笑って感動するようなもの、視聴者の感情の振れ幅を最大限にあっちこっちに揺らして、最後はバンッと明るく終わるものをイメージしました」
――いろいろな要素の中でもミュージカルというのは新鮮ですね。
「それがね、僕は今まで3本の芝居を作・演出しているんだけど、全部ミュージカルなんです。もともとミュージカルを目指していた人間だから。僕自身、大学の時に商業劇団に入っていたんですよ。役者志望ではなく、文芸演出部だったんだけれども」

――ご自身の体験が今回のドラマに生かされているんですね。ホラーの方程式である「自分ごとにできる場所」として、劇団というのは書きやすい題材だったのでしょうか。
「そうですね。若いころの自分の経験がベースになっているから。創作の種というのは自分の経験をもとにしたほうがいいと思うんです。しかも劇団や劇場は、怖い話の宝庫(笑)。いわくつきの場所も多いし、スターになりたい者同士の嫉妬や怨念が渦巻いていて、いろんな噂もある。だから面白いものが書けるなと思いました」
――橋本じゅんさんを中心としたコメディー部分は、怖がりの人も心休まる場面になりそうです。
「(橋本じゅん演じる)重森は、結構笑わせる役どころですね。やっぱり怖いものと笑えるもののメリハリは大事です。人間は、自分の感情があちこち振り回されることを面白いと感じますから」

――先生は第4回でカメオ出演されて、橋本さんと共演されたとか。橋本さんが「鈴木先生と異種格闘技戦を繰り広げた」とコメントされています。
「実は僕、カメオ出演マニアなんです。本来、カメオ出演というのは、チラッと映るだけ。名前も出ないものなんですけど、僕の場合は映るどころじゃすまない(笑)。原作・脚本の立場を利用して、アドリブでセリフをどんどんその場で作り出してしゃべりまくりました。監督は大変だったでしょうけど、面白かったですね」

最後に希望があってパワーを得られる物語
――麻依(生駒里奈)と遠山(須賀健太)の恋愛模様も描かれています。
「そうですね。だから二人の恋愛を追うという楽しみ方もあるし、二人の成長物語でもあります」
――ということは、遠山は最後まで無事なのですか? 彼は「ちょっと見てくる」と一人で行動しがちで、仲間内の怪しい人物のことを最初に疑うなど 「ホラーあるある」な行動をとるので心配なのです。
「大丈夫。僕は『あるある』は絶対やらないから(笑)。それに、遠山は僕がモデルなんですよ」

――そうなんですか! では、そこは安心して見続けます。最後に確認ですが「OTHELLO」も希望の物語なんですね?
「たぶん井口(昇)監督は、ホラーが好きみたいですので、ホラーテイストを強めている感じはします。でも、最後は元気が出ると思いますよ。人間パワースポットがお送りする、怖いながらも最後には希望があってパワーを得られる物語! だから、途中でやめずに最後まで見てください。ちなみに人間パワースポットというのは僕のことです(笑)」
■Profile
鈴木光司(すずき・こうじ)
1957年静岡県浜松市生まれ。慶応義塾大学文学部仏文科卒業。1990年、日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞した「楽園」で作家デビュー。「リング」(’91年)、「らせん」(’95年)など数多くのヒット作品を生み出した。「リング」「らせん」は’98年に同時映画化。また「リング」は2002年にハリウッドでもリメイクされた。原作・脚本をつとめる「OTHELLO」は、’20年の「あの子が生まれる…」(FODオリジナル配信)以来の書き下ろし作品となる。

「OTHELLO」放送情報
ABCテレビ 毎週日曜 深0:25~
撮影/尾崎篤志 取材・文/加治屋真美