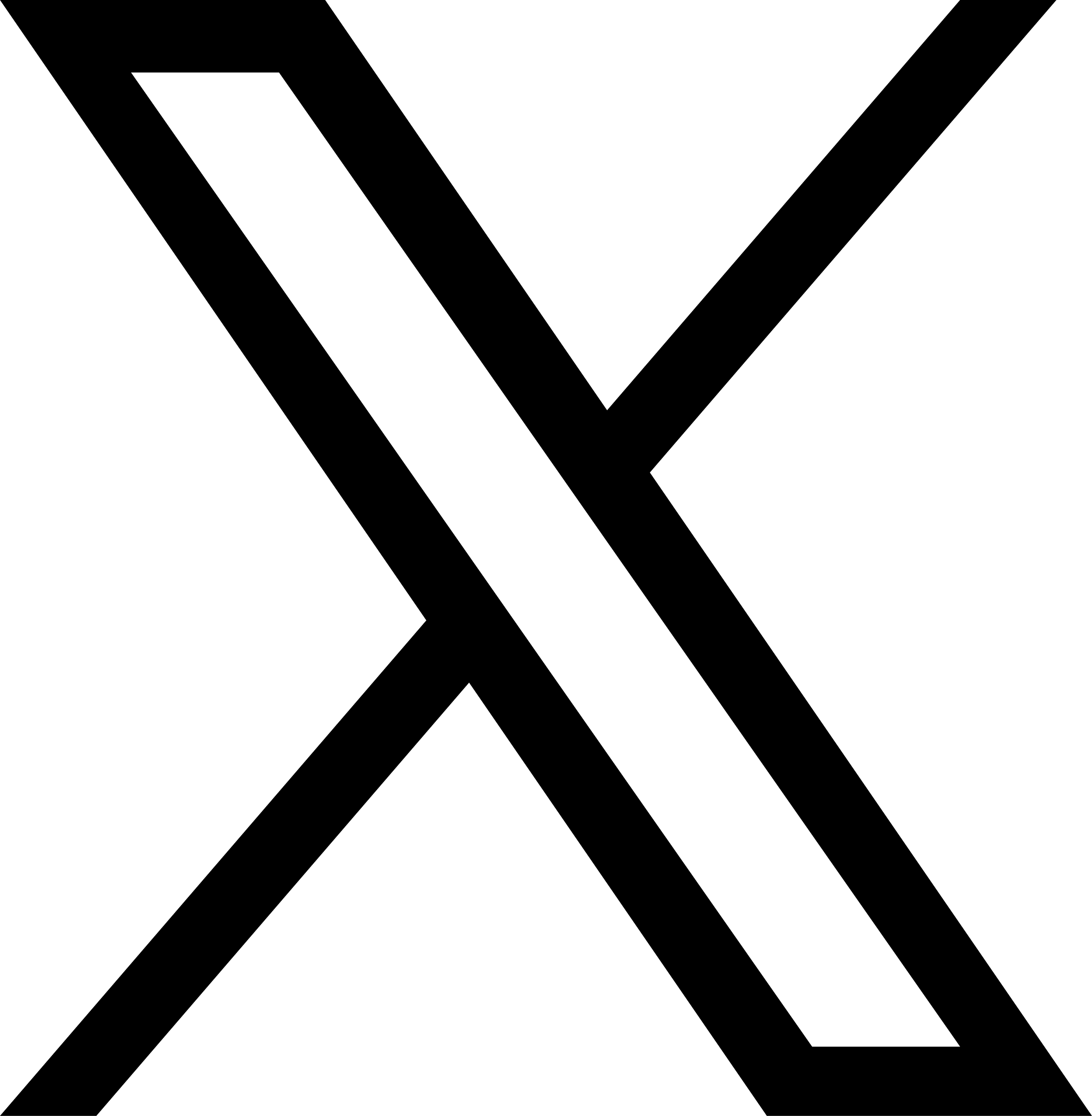ドラマ「岸辺露伴は動かない」シリーズもエピソードを重ねること第9話。今回は、当初より映像化が期待されていた人気エピソード「密漁海岸」。「ジョジョの奇妙な冒険 第4部」本編に登場したキャラクターのトニオ・トラサルディーと、杜王町の海岸で“密漁”に挑む。主演の高橋一生さんに、過酷だった水中での撮影の舞台裏やCGではなくアナログを追及する理由、また、リハーサルから本番まで「熟成」させるという、この作品ならではの芝居の神髄について、たっぷり伺いました。最後は高橋さんの「ジョジョ愛」も垣間見られるインタビューを、どうぞ!!
水中での撮影は臨場感があり、且つ、ある意味芸術的なカットに仕上がっているのでは
――2020年にドラマとしてスタートした「岸辺露伴は動かない」も5年目になります。制作統括の土橋圭介さんが、「コロナ禍にスタートしたので、初めてマスクなしで全編を撮ったのが感慨深かった」とおっしゃっていました。
「僕も同じ思いですし、感動した出来事でした。今回初めて顔の全貌を確認できたスタッフの方が多々いらして。僕はスタッフの方々を最初のお客さんだとも思っていますし、これだけ長く一緒に撮影をさせていただいているチームの皆さん一人ひとりの笑顔や充実した顔、反応してくださる姿を確認しながら撮影していくことができて、久しぶりに『お芝居をやっていて楽しいな』と思えるエネルギーが強く伝わってくる現場でした」
――「密漁海岸」は岸辺露伴シリーズの中でも人気の高いエピソードです。海が舞台の一つになっているので、水中での撮影も多く、大変だったのではないでしょうか。渡辺一貴監督曰く、「(高橋さんに)今までで一番体を張っていただいている」とのことですが…。
「体を張っているということで言えば、思った以上に第4話の『ザ・ラン』は(体に)来ていましたけれど(笑)、今回、『肺は本当に浮き袋なんだな』と実感しました。呼吸をしないで息を吐き切った状態で沈んでいかないと、体って沈まないんです。逆にカットがかかった後、上がっていけないということもあって、水の中はこんなにも自由が利かないんだな、と思いました。(専用のプールの)水深10mくらいのところからスタートして、だいたい5mくらいのところで沈んだり上がったりしていました」

――想像するだけで苦しそうです…。
「ただ、僕はもう何度か完成したものを見せていただいているんですが、『あんまり伝わっていないな』とは思っています(笑)。息ができなくて一瞬で気を失いそうになりましたし、僕の中ではもっととんでもないことが起きていた感覚でしたから。水中撮影のチームも来てくださって、何日かに分けて撮影をしたのですが、これまでも一緒にやってきたかのように皆さんチームワークよく、『このアワビに、見えないように重しを仕込もう』とか、僕を沈めさせようとする画策をたくさんしてくださったおかげで(笑)、映像としては臨場感があり、且つ、ある意味芸術的なカットに仕上がっているんじゃないかなと思っています」


今作でもCGはほぼ不使用。タコ、ものすごく動いているので注目してください
――キーパーソンとなる料理人、トニオ・トラサルディー役のアルフレッド(Alfredo Chiarenza)さんとの共演はいかがでしたか?
「アルフレッドと現場で会った瞬間に『トニオだ!』と思ったほど、説得力を持って現場にいてくださった印象です。とても実直に役に取り組んでいらして、日本語も完全にこなし、目線の交わし合いなど、しっかりとお芝居を受けてくださいました。トニオのキャラクターとともにアルフレッドの人柄もにじみ出ているんじゃないかなと思っています」
――今作ならではの特徴や見どころを教えてください。
「作品としては、前後半に分かれていると僕は思っているんです。前半、『ジョジョの奇妙な冒険 第4部』のあるエピソードから始まって、後半の『岸辺露伴~』の原作につながっていくような構成で、後半は前半とは打って変わってアクティブな話になっています。とはいえ、やはり全体的に『露伴』らしい、暗くゴシックなテイストで進んでいきますし、そこに菊地(成孔)さんのセンスで日本的な音楽が入ってきて、とても面白いものになっていると思います。また、CGをほとんど使ってないというのも見どころと言いますか。今作に限らず、『岸辺露伴』の現場では“アナログでどこまで行けるか”ということを追求しているので、ネタバレになってしまわない程度に言うと…タコ、ものすごく動いています(笑)。そういうところにも注目していただければと思います」

原点に戻って、第2期や映画の芝居とはちょっと違うやり方をしているかもしれない
――第1、2、3期、そして映画「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」と、毎回、お芝居のテーマ性やスタンスを変えているとおっしゃっていますよね。今作にはどのように臨まれましたか?
「誤解を恐れずに言うと、ある程度デフォルメしているので、たぶん原点に戻っています。ですから、第2期や映画におけるお芝居とは少し違うやり方をしているかもしれません。特に密室においてです。毎回、密室劇テイストのようなものがどこかに必ずあって、その中でじわじわ来るもの、という感じは同じだと思います。例えば、第1話の『富豪村』ではある村の屋敷、第2話の『くしゃがら』では露伴邸で、映画『~ルーヴルへ行く』ならZ-13倉庫、それが今回は海中ということになるわけですが、わりと動きが限られるので、そこでどれだけ躍動できるか。シチュエーションによって大きく変わってきますので、ある程度拡大したほうがいいのか、縮小してもいいのか、ときには別に暴れなくてもいいところで暴れ回ってみたり…、それぞれの見え方を考えながら、お芝居の質を変えているように思います」
――それは毎回、そうしよう、と意識的に思っていらっしゃるんですか。
「というより、現場に入ってみてからです。リハーサルは事前にやらせていただいていますが、例えば、床一つとっても、リハをカーペットでやっていて、現場は木だったら、質感というか肌感が全然違います。ですから現場で初めて、『ここは転がったほうが面白そうな床か?』とか『この床を撮ってもらいたいから突っ伏してみようか』とか『このソファーも使いたいな』とか、いろんなことを考えていくわけですが、そういう感じはお芝居の方向感覚というか平衡感覚として持っているような気がします」


――特に細かく演出があるわけではないんですね。
「ただ(演出の渡辺)一貴さんの素晴らしいところだと思うんですが、現場はこんな風になっている、という写真を全部ずらっと並べて事前に見せてくれて、撮影とは別日にリハーサルを行わせてもらえるんです。セリフはその場で定着させることももちろんできますが、本来、頭に入れるだけではなく、どれだけ体に馴染んでいくかということだと思いますし、定着してから放っておくことはある意味“熟成”ですから。そういうことができる土壌を作ってくれているんだと思います。リハーサルをしっかりとやれたほうが、本番までにみんな持ち帰れるものがたくさんありますし、一貴さんはそういう部分をしっかりと考えてくださっている方なんだなと実感しています」
――ドラマでも映画でも、カメラアングルにもとてもこだわりを感じますが、そういうものも現場で決まっていくんでしょうか?
「そうです。そもそも一貴さんはおそらく、露伴がどういう風に映ったらいいか、というアイデアはストックとしてたくさん持っていると思うんです。僕が演じる露伴のどの角度が一番いいのかということはもちろん、例えば、どの角度だと、笑っているか笑っていないかが見えるか、というようなところまでとても丁寧に探ってくれています」
――もちろんこの5年の積み重ねもあるでしょうけれど、作品づくりへの情熱と愛を感じます。
「今やもう、とても稀有な方だと思います。これだけ分かりやすいものがあふれている今、あえて分かりにくいことをやって、『ここから面白いものを抽出してくださいよ、お客さん』という。そんな風にやってくださる演出家の方はなかなかいないでしょうね」

一貴さんから「タコやアワビを実際に作ります」と聞いて、「正しいと思います」と
――先ほど、「岸辺露伴の現場では、“アナログでどこまで行けるか”ということを追求している」というお話をされていましたが、渡辺さんがアナログにこだわるのは「好きだから」だそうですね。至極シンプルゆえ、強い思いを感じます。今作では水中での戦闘シーンに加えて、海洋生物も登場するので特に難しそうでしたが、この5年を見てもCGなどテクノロジーの進化がめざましい中、そういった渡辺さんのポリシーに改めて感じることはありますか?
「CGも最初の頃はよかったと思います。僕も、2000年の少し前ぐらいは、CGがふんだんに使われている映画を見て、『おーっ!』となっていましたが、もしかしたら飽和状態になっているのかもしれないなと」

――確かに、なんでもかんでもCGで表現できてしまうというか、当たり前になっているのは否めません。
「だから僕は、どこかアナログな(ロバート・)ゼメキス監督のCGの使い方がとても好きなんです。(クリストファー・)ノーラン監督も、いろいろ調べてみたところ、例えば宇宙船を爆発させるというときに、小さいミニチュアの模型でやると、爆発の速度もはじけ飛び方も全然違うので、20分の1ぐらいの模型を作って破壊しているのだそうです。模型と言っても、ものすごく大きいんですけれど、結局、模型を使ってやっていると考えると、やっぱりどこまで行ってもアナログの質感には勝てないということです」
――リアルさを追求するにはCGでは限界があるように思いますよね。
「映画『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』(’08年)では、主人公が老人から若返っていく姿をCGで表現していますが、『目が一番難しかった』という制作陣の話を聞いて、とても特徴的だと思ったんです。つまり、人間の目はCGではできないんだ、と。人は、お芝居をするときもそうですが、相手の皮膚やその他のディテールよりも目を一番見ているので、目の動きが不自然だと、すぐに見分けることができるのだそうです。僕も、それに近しい世界観の中にいる者として、一貴さんの『アナログにこだわりたい』という意見を聞いて、いつも『本当にその通りだと思います』と思いながらお芝居をしています。今回も、『タコは実際に作ります。アワビも作っています』と言っていたので、『正しいと思います』と思っていました」

やっぱり「ヘブンズ・ドアー」が一番好き。敵う人はほとんどいないんじゃないでしょうか
――ちなみに以前、渡辺さんのインタビューをさせていただいた時に、好きなスタンドをうかがったら、「パール・ジャム」だとおっしゃっていました。今作ではそのスタンドを持つトニオが登場しますが、そういったお話を現場でされたりしましたか?
「現場でスタンドの話をすることはとくになかったですね(笑)。僕もいまだに『パール・ジャム』は好きだなと思いますが、これだけ自分のギフト(特殊能力)の話になってきていて、ギフトで目の前の困難をどう乗り越えていくか、という局面に立たされるので、やっぱり『ヘブンズ・ドアー』はいいなと思います」
――高橋さんが一番好きなスタンドを聞かれたら、「ヘブンズ・ドアー」になりますか?
「そうですね。敵う人、ほとんどいないんじゃないでしょうか。でも、荒木(飛呂彦)先生が描こうとしていらっしゃるスタンドがこれだけいっぱいある中で、圧倒的な強さを持つというのはなかなか難しいことで。戦ったり修行したりして強くなっていくというよりも、精神性におけるもので、どの機転で切り抜けるか、という話なので、相手がどんなスタンドを持っていても勝つ可能性がある。それが昔から僕が好きなパワーバランスなんです。例えば、ハイウェイ・スター戦(「ジョジョの奇妙な冒険 第4部」)において、(東方)仗助は戦っていますけれど、『露伴だったらいけるだろうな』と僕は思っているんです。パワーだけで一点を穿とうとする力ではなくて、精神性とか哲学性、自分のこだわりで戦っていくので、『あの局面、露伴だったらどう乗り越えるか』ということは考えます。そう考えると、荒木先生の世界におけるパワーバランスはすごいなと改めて思います。もしかしたら、重ちー(矢安宮重清)の『ハーヴェスト』(「ジョジョの奇妙な冒険 第4部」)で勝てる可能性だってありますから。全然分からない。だからこそ、面白いんでしょうね」

■Profile
高橋一生(たかはし・いっせい)
1980年12月9日生まれ。東京都出身。ドラマ、映画、舞台など幅広く活躍。2024年4月クールは主演ドラマ「6秒間の軌跡~花火師・望月星太郎の2番目の憂鬱」(テレビ朝日)が放送中。6月30日(日)放送の「テレビ朝日プレミアム ブラック・ジャック」に主演。

「岸辺露伴は動かない」放送情報
NHK総合
5月10日(金)後10:00~
撮影/尾崎篤志
取材・文/四戸咲子